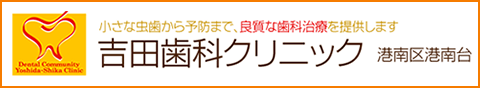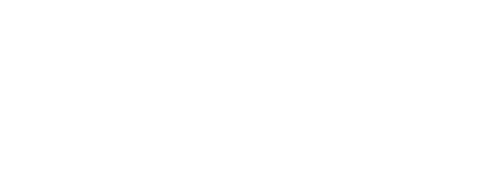整形外科疾患への漢方薬治療

疾患には急性期と慢性期がありますが、整形外科疾患も同様に急性期と慢性期が存在します。漢方治療といえば、慢性期疾患治療の選択肢の一つという考え方をされがちですが、整形外科疾患においても急性期と慢性期に使い分けることで有効な治療方法となります。
当院では整形外科疾患全てを漢方治療しているわけではありませんが、大きな武器の一つとして有効活用しています。
鎮痛剤についてはNSAIDS(非ステロイド性抗炎症薬:ロキソニンなど)がCKD(慢性腎臓病)の患者さんや、心機能にトラブルを抱えている患者さん、消化性潰瘍の既往がある患者さんには使えないなど、非常に制約があります。
NSAIDSが使いにくい症例には漢方治療は大きな武器となります。
また、過去に処方されていた鎮痛剤が無効で服薬に抵抗がある高齢の患者さん、妊娠・授乳中で西洋薬の服薬をためらう女性、小児の腰痛にも漢方は非常に心強い選択肢であると考えています。
急性期
急性期の整形外科疾患としては、
- 外傷(骨折、靱帯損傷などの軟部組織の損傷)
- 慢性脊椎疾患(脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症)
- 感染症
が大別されます。
いずれにおいても診断をつけた上で、現疾患の西洋医学的な治療を滞りなく行うことが原則です。
整形外科領域で主に使う薬剤は、消炎鎮痛薬と抗菌薬がメインであり、感染症に対しては漢方で代用することは絶対にありません。
骨折・捻挫・筋挫傷
急性期は内出血・浮腫に伴う組織の炎症反応が主な病態であると考えます。
治療の原則としてはRICE(安静rest、冷却icing、圧迫compression、挙上elevation)療法であり、固定や必要に応じて手術への流れを滞りなく行うことが原則であるのは間違いありません。
外傷は、瘀血(おけつ)と水滞が主であるので、使用方剤は駆瘀血剤(くおけつざい)の治打撲一方に、利水剤の五苓散を併用することが多いです。
NSAIDSについては、急性期に漫然と使うものではなく、急性外傷で処方することは患者さん側がよほど処方を希望されない限りは、処方しないことにしています。
※外傷の内出血・浮腫という局所の症状=「瘀血(おけつ)」、すなわち血の滞り。
急性腰痛症
いわゆる「ぎっくり腰」。椎間関節の捻挫による痛みと傍脊柱筋に痛み刺激を起こし、結果として筋肉のスパスムを引き起こすと考えられています。
腰痛の急性期には芍薬甘草湯を高容量で短期間使用します。芍薬甘草湯には平滑筋も横紋筋も同時に抑える作用があると言われており、よく知られている「こむら返り」だけではなく、頚部痛や腰痛にも効果があります。この場合は、NSAIDSを必要に応じて服用してもらっています。
高齢者の椎体骨折による急性腰痛に対しては、骨折と同じ考えであるので駆瘀血剤の治打撲一方を使用します。ただ、痛みによる体動の減少で便秘傾向になりがちなので西洋薬の緩下剤を併用することも多いです。
漢方自体を桃核承気湯に変更することもあります。
この場合、「痛み止めは出ないのか?」という質問を頂くことが非常に多いですが、高齢患者さんの場合は他剤を多く服薬している場合も多く、飲み合わせの問題や服薬薬剤の増加のリスクについてお話しし、治打撲一方が有効な鎮痛作用を持つことをお話しすると、だいたいの患者さんは納得していただいております。
副作用と服用期間

芍薬甘草湯に関しては、甘草の副作用の点から2週間以上は使わないようにしています(血圧が上がる)。急性期を脱し、痛みが落ち着いた患者さんには漫然と服用することなく、やめるようにしています。慢性期に入れば、西洋薬や漢方薬を併用することが多いです。
表:急性期の整形外科疾患によく用いる方剤(出典:沖縄県立中部病院整形外科 普天間 朝拓先生)
※診療時間表が全て見られない場合は横スクロールでご覧ください。
症状・疾患 |
方剤 |
使用目標 |
|---|---|---|
骨折・捻挫・筋挫傷 |
治打撲一方(+五苓散) |
内出血(瘀血)・浮腫(水滞) |
治打撲一方(+柴苓湯) |
病変が末端にある場合 |
|
術後の浮腫・炎症 |
補中益気湯+治打撲一方 |
内出血(瘀血)・浮腫(水滞) |
急性腰痛症 |
芍薬甘草湯 |
第一選択 |
治打撲一方 |
高齢者の椎体骨折 |
|
治打撲一方+大黄甘草湯 |
便秘 |
|
桃核承気湯 |
便秘 |
慢性期
慢性期の整形外科疾患は骨粗鬆症、変性疾患(変形性膝関節症、変形性脊椎症、変形性股関節症)、肩関節周囲炎と挙げられ、60歳以降の患者さんが多いです。これらの年代の患者さんは慢性疾患として他の薬剤を服薬しているケースが多いです。
鎮痛剤も、「痛み」の訴えがあればNSAIDSを約束処方のように処方しがちです。もちろん、疾患によってキードラッグは存在する(急性期関節炎のNSAIDS、関節リウマチのMTXなど)ので、薬の足し算にならないように漢方をアシストとして使うのは非常に有意義なことだと考えています。
頸肩腕症候群
いわゆる肩こり。
肩こりの原因となる姿勢や生活習慣を聞いたのちに、ストレッチ指導や生活習慣の改善をアプローチとし、場合によってはトリガーポイント注射も行い、それでも軽快しない場合は葛根湯を併用としています。
麻杏よく甘湯も著効するときがあります。ベースが葛根湯であり、上肢のしびれを伴う患者さんには桂枝加朮附湯を使うこともあれば、精神的要素が強い患者さんには気鬱へ働きかける柴胡剤を処方することがあります。
頸椎捻挫
寝違えや交通事故による頚部痛である頸椎捻挫は外傷であるので、治打撲一方を処方します。他の処方は急性期を終え、その後の症状によって処方分けを行っています。
たとえば、「入浴して調子が良くなりますか(温めると調子が良くなるか?)」という問いに対し、「温めると良いようです」という答えがあれば、温める薬を使うことになると言う具合です。
交通事故の場合は疼痛が遷延化する症例や、心因性疼痛の場合も少なくないので、その際は途中から柴胡剤を用いることも多いです。
肩関節周囲炎
肩関節周囲炎には疾患の背景にインピンジメント症候群、腱板損傷、腱板炎、関節唇損傷等
考慮鑑別すべき病態があり、診断をつけるのはもちろん大事なのですが、「痛み」に対しては二朮湯を処方します。
全てを漢方治療しているわけではなく、肩関節腔や肩峰下滑液包にヒアルロン酸や局麻+ステロイド注射を用いた上で、補助的役割として処方しています。
慢性期に用いる漢方処方(上肢)
※診療時間表が全て見られない場合は横スクロールでご覧ください。
症状・疾患 |
方剤 |
使用目的 |
|---|---|---|
頸肩腕症候群 |
葛根湯 |
第1選択 |
桂枝加朮附湯 |
上肢のしびれ |
|
柴胡桂枝湯 |
精神症状 |
|
柴胡桂枝乾姜湯 |
精神症状 |
|
頸椎捻挫 |
治打撲一方 |
急性期 |
桂枝茯苓丸 |
瘀血所見 |
|
桂枝茯苓丸加よく苡仁 |
瘀血所見 |
|
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
冷え |
|
麻黄附子細辛湯 |
当帰四逆加呉茱萸生姜湯が効かないとき |
|
肩関節周囲炎 |
二朮湯 |
第1選択 |
麻杏よく甘湯 |
第2選択 |
|
桂枝茯苓丸 |
瘀血所見 |
慢性期に用いる漢方処方(下肢)
※診療時間表が全て見られない場合は横スクロールでご覧ください。
症状・疾患 |
方剤 |
使用目的 |
|---|---|---|
腰痛 |
桂枝加朮附湯 |
冷え症、胃腸障害、寒冷刺激で痛みが増す |
芍薬甘草湯 |
傍脊柱筋の緊張を伴う腰痛の悪化 |
|
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
しもやけ、あかぎれの既往、寒冷で痛みが増す |
|
温経湯 |
冷えがあるが、胃腸障害がある |
|
真武湯 |
自覚のない冷え、新陳代謝の低下 |
|
下肢の痛み・しびれ |
桂枝茯苓丸 |
瘀血所見 |
当帰芍薬散 |
瘀血所見に加えて水毒 |
|
八味地黄丸 |
腎虚 |
|
牛車腎気丸 |
腎虚に浮腫などの水毒を伴う |
|
附子末 |
冷えや疼痛が強い、浮腫などの水毒傾向 |
|
変形性膝関節症 |
防已黄耆湯 |
色白・水太り、重度OA変化ではないこと |
よく苡仁湯 |
局所の腫脹・熱感、関節拘縮 |
|
麻黄附子細辛湯 |
炎症はあるが、麻黄剤が使いにくい場合 |
|
骨折・捻挫の後遺症 |
桃核承気湯 |
実証・瘀血による臍傍圧痛・便秘・のぼせ |
治打撲一方 |
便秘傾向のある外傷後の陳旧例 |
|
大柴胡湯 |
腹診で胸脇苦満 |
|
桂枝茯苓丸 |
NSAIDSが使いにくい症例 |
|
抑肝散 |
表に出るイライラ、不満 |
|
加味逍遙散 |
非論理的な訴え、多愁訴、移り変わる症状や部位 |
|
半夏厚朴湯 |
几帳面・予期不安 |
|
附子末 |
通常の消炎鎮痛剤で効果が得られない疼痛 |
腰痛
桂枝加朮附湯は麻黄を含まないので副反応のリスクが低く、NSAIDSが使いにくい高齢患者さんの腰痛や慢性疼痛、下肢神経痛、四肢関節痛にと幅広く用いることができる非常に使い勝手の良い薬剤です。
長くNSAIDSを服薬している症例、服薬数が多い症例には一度は処方しておきたい薬剤と考えています。
下肢痛、下肢のしびれ
整形外科外来でよく聞く「下肢痛、しびれ」。高齢患者さんに多い訴えであります。
西洋医学的には物理的な神経圧迫、動脈硬化による血流障害、運動障害・排尿障害・代謝低下による浮腫など複数の原因が絡んでいることが少なくありません。
勤務医時代に血管拡張作用のある薬剤(プロスタンディン、パルクス、リプル等)の点滴で症状が軽快する症例が多数あったことから(主訴として症状が軽快した)、下肢神経症状の原因の多くは、「瘀血」にあるのでは?と考えるに至りました。
桂枝茯苓丸や当帰芍薬散はこれらの「瘀血」を主とした症例には、漢方が服薬できるのであれば漫然と鎮痛剤を服薬するより、処方してみる価値はあるのではないでしょうか。
補腎剤(八味地黄丸、牛車腎気丸)は高齢者に合併する多種多様な症状や疾患を漢方1剤でカバーするという、漢方方治療の理想と言っても良いかもしれません。下肢症状が前面に出た多彩な愁訴を持つ患者さんに処方することが多いです。
変形性膝関節症
変形性膝関節症の漢方治療適応はレントゲン写真で関節列隙が残存する症例までで、重症例(Grade3以上)には残念ながら効果はありません。
関節水腫を伴うような症例にも無効でしょう。数例に処方してみたことはありますが、全く効果はありませんでした。
ヒアルロン酸注射と平行して処方することも多いですが、重症例に関してはヒアルロン酸も効果が期待できないので、どのタイミングで人工関節や骨切り術等の手術に踏み切るか、もしくは保存的加療で行くのかを患者さんの生活スタイルと併せて、よく話し合うことが大切であると実感しています。
効果判定
漢方薬の効果判定は、VAS(visual analogue scale)で評価します。高齢患者さんの場合は最低でも1ヶ月、通常は1ヶ月半~2ヶ月を目安にします。もちろん、副反応の確認をしないといけないので初回処方は2週間から、です。
服薬しないと効果判定できないので、「漢方、苦くて飲めないよ」や「粉が飲みづらい」という患者さんには無理強いできないのが大きな欠点です。
参考文献
- 新見正則:本当に明日から使える漢方薬、2010
- 松田邦夫、稲木一元:臨床医のための漢方、1987
- 大塚敬節:漢方の特質、1971
- 松田邦夫:症例による漢方治療の実際、1992
- 日本医師会 編:漢方治療のABC、1992
参考資料
- 株式会社ツムラ:TUMURA KAMPO FORMULATION FOR PRESCRIPTION
- 宮原 桂:漢方ポケット図鑑、2008